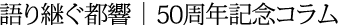都響 マーラー演奏の軌跡(上)

創立20周年記念演奏会。ズデニェック・コシュラー指揮、総勢1,008名で《千人の交響曲》を演奏。
(1985年10月1・2日/東京文化会館)
©木之下晃
「マーラー・オーケストラ」として注目を集める都響。その伝統を築くまでの軌跡を、音楽評論家・東条碩夫氏にお寄せいただいた演奏史とともに振り返ります。今回は創立から1990年代前半まで。
都響 マーラー主要演奏歴(創立~1990年代前半)
| 1969年6月19日 | 森正指揮で《大地の歌》(都響によるマーラー初演奏)。 |
| 1973年7月~77年12月 | 渡邉暁雄指揮で第1番《巨人》、第4番、第5番、第6番《悲劇的》、第7番、《大地の歌》、第10番(クック版全曲/日本初演)。 |
| 1982年3月31日 | モーシェ・アツモン指揮で第2番《復活》(通算で交響曲の全曲演奏を達成)。 |
| 1988年10月~91年10月 | 若杉弘=都響/サントリーホール マーラー・シリーズ (サントリーホールとの共催/都響初のマーラー交響曲全曲演奏会) |
黎明期と渡邉暁雄のマーラー連続演奏
1960年代に入り、わが国のオーケストラのプログラムにもマーラーの交響曲が少しずつ乗りはじめていたが、まだほんの限られた数に過ぎなかった。それゆえ、65年10月に第1歩を踏み出した東京都交響楽団が、最初の7年間にマーラーの交響曲をたった2曲(69年に《大地の歌》、71年に第1番《巨人》、いずれも初代音楽監督・森正の指揮)しか演奏しなかったとしても、別に不思議はない。そもそもマーラーの交響曲そのものが、未だレパートリーに定着していなかった時代なのである。
 都響がマーラーの交響曲に本格的に取り組みはじめたのは、第2代音楽監督兼常任指揮者の渡邉暁雄の時代(72年4月~78年3月)であった。彼は、73年7月12日定期での第4番を皮切りに、第5番(同12月)、第7番(74年12月)、《大地の歌》(75年12月)、《巨人》(76年10月)、クック校訂版の第10番(日本初演/同12月)、第5番(77年3月)、《さすらう若人の歌》と第6番《悲劇的》(同12月)――という順で指揮していった。第2、3、8、9番こそ取り上げていないものの、決して少ない数ではなかろう。
都響がマーラーの交響曲に本格的に取り組みはじめたのは、第2代音楽監督兼常任指揮者の渡邉暁雄の時代(72年4月~78年3月)であった。彼は、73年7月12日定期での第4番を皮切りに、第5番(同12月)、第7番(74年12月)、《大地の歌》(75年12月)、《巨人》(76年10月)、クック校訂版の第10番(日本初演/同12月)、第5番(77年3月)、《さすらう若人の歌》と第6番《悲劇的》(同12月)――という順で指揮していった。第2、3、8、9番こそ取り上げていないものの、決して少ない数ではなかろう。
渡邉暁雄の指揮するマーラーは、いかにも彼らしく、端整な演奏であった。いわゆる忘我的な熱狂、官能的な陶酔感、激情の爆発というタイプの演奏ではないために、ドイツ後期ロマン派の作品に向いた指揮者ではないという批評もあったくらいだが、しかし第4番や第5番などは、すこぶる聴衆を沸かせた演奏であったことを記憶している。
「マーラーの得意な指揮者はたくさんいますから、都響はぜひマーラーをこれからもとりあげていってほしいと思います」と渡邉は退任に際し、そう言い残した。だが当時は、都響がやがてマーラーの交響曲を十八番のレパートリーにし、「都響のマーラー」を看板に人気を集めることになるとは、まだほとんどだれも予想していなかったのである。

渡邉暁雄
渡邉暁雄の指揮するマーラーは、いかにも彼らしく、端整な演奏であった。いわゆる忘我的な熱狂、官能的な陶酔感、激情の爆発というタイプの演奏ではないために、ドイツ後期ロマン派の作品に向いた指揮者ではないという批評もあったくらいだが、しかし第4番や第5番などは、すこぶる聴衆を沸かせた演奏であったことを記憶している。
「マーラーの得意な指揮者はたくさんいますから、都響はぜひマーラーをこれからもとりあげていってほしいと思います」と渡邉は退任に際し、そう言い残した。だが当時は、都響がやがてマーラーの交響曲を十八番のレパートリーにし、「都響のマーラー」を看板に人気を集めることになるとは、まだほとんどだれも予想していなかったのである。
モーシェ・アツモンと客演指揮者たち
しかし、78年4月に新しいシェフ――ミュージック・アドヴァイザー兼首席指揮者に就任したモーシェ・アツモンは、就任最初の定期(79年1月)でマーラーの第5番を取り上げた。どちらかといえば前任者の渡邉に似た端整な造型感覚を備えた指揮表現で、ことさらにマーラーの交響曲に適した人とも思えなかったアツモンが、名刺代わりの最初の定期にこの曲を演奏するとは意外だったが、今にして思えばこういうところにも都響とマーラーとを結ぶ不思議な因縁の力が作用していたのかもしれない。とにかく陶酔感や激情は感じられなかったけれどもがっちりと組み立てられた、清新なマーラーであったという記憶がある。彼は83年3月までの任期の間に、第9番(80年10月)と第2番《復活》(82年3月)を指揮したが、都響が演奏した《復活》の、これが最初のものとなった。
 ちなみにこのアツモン時代、彼以外に都響でマーラーを振った指揮者は、他に3人いる。まず、正指揮者のポストに在った小林研一郎である。79年12月に《巨人》を、82年5月に第5番を指揮して、いずれも大絶賛を受けた。また79年7月には若杉弘が初めて定期に登場したが、この時に指揮したのが第3番である。続いて81年9月定期にはガリー・ベルティーニが初お目見えしたが、その2つの定期のうちのひとつに含まれていたのは第6番《悲劇的》であった。
ちなみにこのアツモン時代、彼以外に都響でマーラーを振った指揮者は、他に3人いる。まず、正指揮者のポストに在った小林研一郎である。79年12月に《巨人》を、82年5月に第5番を指揮して、いずれも大絶賛を受けた。また79年7月には若杉弘が初めて定期に登場したが、この時に指揮したのが第3番である。続いて81年9月定期にはガリー・ベルティーニが初お目見えしたが、その2つの定期のうちのひとつに含まれていたのは第6番《悲劇的》であった。
ベルティーニは、60年にイスラエル・フィルの副指揮者として来日したことはあるが、日本では知る人ぞ知る的な存在。しかもあのマーラー交響曲全集で有名になるケルン放送響首席指揮者には未だ就任していなかった時代である。しかし、この時の演奏について故・中河原理氏が『音楽の友』誌上で「稀にみる名演、迫真のマーラー。日本のオーケストラがマーラーをこれほどきれいに鳴らしたことはあったかどうか……雄渾、壮大にして熱狂的なマーラー」と絶賛している。
このように、アツモンだけでなく、のちに都響のマーラー・ツィクルスの顔となる若杉とベルティーニが(そして後述のインバルまでも)、いずれも定期デビューの月にマーラーの交響曲を取り上げていたのは興味深い。都響は、まるでマーラーを得意とする指揮者ばかり選んでシェフに招いていたかのようではないか。

モーシェ・アツモン
ベルティーニは、60年にイスラエル・フィルの副指揮者として来日したことはあるが、日本では知る人ぞ知る的な存在。しかもあのマーラー交響曲全集で有名になるケルン放送響首席指揮者には未だ就任していなかった時代である。しかし、この時の演奏について故・中河原理氏が『音楽の友』誌上で「稀にみる名演、迫真のマーラー。日本のオーケストラがマーラーをこれほどきれいに鳴らしたことはあったかどうか……雄渾、壮大にして熱狂的なマーラー」と絶賛している。
このように、アツモンだけでなく、のちに都響のマーラー・ツィクルスの顔となる若杉とベルティーニが(そして後述のインバルまでも)、いずれも定期デビューの月にマーラーの交響曲を取り上げていたのは興味深い。都響は、まるでマーラーを得意とする指揮者ばかり選んでシェフに招いていたかのようではないか。
定期招聘指揮者の時代/コシュラーの《千人》
都響には、アツモンのあと、83年4月から86年3月までの期間、「定期招聘指揮者」という時代があった。特定のシェフを置かず、ズデニェック・コシュラー、ジャン・フルネ、ペーター・マークの3人が中心になるという、いわば「トロイカ体制」である。この中でマーラーを振りそうな指揮者といえば、コシュラーしかいないだろう。彼は、84年9月の第200回記念定期で《復活》を、85年10月の創立20周年記念演奏会(特別演奏会とA定期)では第8番《千人の交響曲》を指揮した。後者では、本当に1,008人の演奏者を舞台に乗せたという――これは写真で見てもすこぶる壮観である。この時の演奏を、藤田由之氏は『音楽の友』で「巧まずしてその音楽の内側に迫ってゆくようなアプローチ」と称賛したのであった。
圧倒時な足跡を残した若杉弘
そして、「都響のマーラー」に圧倒的な足跡を残すことになる若杉弘が、86年4月、第3代音楽監督に就任する(翌年度より首席指揮者も兼任)。前述のように79年7月の定期デビューで第3番を指揮した彼は、84年7月16日の特別演奏会でも「若き日のマーラー」と題し《花の章》《さすらう若人の歌》《巨人》を指揮したが、これもまたいかにも彼らしいコンセプトを持ったプログラムといえよう。
 そしてついに、《大地の歌》と第10番の「アダージョ」を含む都響最初の「マーラー・シリーズ」(交響曲全曲演奏会)を開催した(88年10月22日~91年10月18日)。その際、《巨人》はブダペスト初演稿に基づく改訂稿(《花の章》を含む/日本初演)を、また《復活》では第1楽章にその第1稿ともいうべき《葬礼》(日本初演)を使用するなど、大向こうを唸らせるアイディアを盛り込んだ。「ダイヤの原石ともいえる部分を聴いていただくと、現在決定版とされている音楽の姿が、ああこういう所からこういうふうに磨かれて来たのかと判ると思うし、僕もオケや聴衆と一緒にそれを追体験できると思うのです」というコンセプトなのであった(『週刊FM』89年3月6日号、筆者との対談から)。
そしてついに、《大地の歌》と第10番の「アダージョ」を含む都響最初の「マーラー・シリーズ」(交響曲全曲演奏会)を開催した(88年10月22日~91年10月18日)。その際、《巨人》はブダペスト初演稿に基づく改訂稿(《花の章》を含む/日本初演)を、また《復活》では第1楽章にその第1稿ともいうべき《葬礼》(日本初演)を使用するなど、大向こうを唸らせるアイディアを盛り込んだ。「ダイヤの原石ともいえる部分を聴いていただくと、現在決定版とされている音楽の姿が、ああこういう所からこういうふうに磨かれて来たのかと判ると思うし、僕もオケや聴衆と一緒にそれを追体験できると思うのです」というコンセプトなのであった(『週刊FM』89年3月6日号、筆者との対談から)。
なお彼はそのツィクルス以外でも、95年3月までの任期中に、86年7月の特別演奏会で《交響的前奏曲》(日本初演)と《子供の魔法の角笛》を、86年10月のサントリーホール・オープニングシリーズで《千人の交響曲》を指揮した他、87年にはクック版第10番の全曲と第4番を取り上げており、88年には第9番と《リュッケルトの詩による5つの歌》、92年には《嘆きの歌》を、94年にはベリオ編の《若き日の歌》(日本初演)を演奏している。そして任期最後の定期(95年3月)には、第9番を指揮したのだった。
これほどマーラーを数多く都響で指揮した彼だったが、その一方で、行きすぎた「マーラー・ブーム」という傾向には危惧を抱いていた。「あんまりイージーにマーラーをやり過ぎるのは危険だと思う。そうやってるといつかはお客様が、効用逓減の法則じゃないけど、もうマーラーは結構、という時期が来て、こんなに素晴らしい音楽なのに価値が下がってしまわないとも限らない」(同前)。
だがやはり、客演指揮者たちもマーラーの交響曲を指揮した。その80年代から90年にかけて、ベルティーニの他にも、アダム・フィッシャー、ヘルベルト・ケーゲル、山田一雄、井上道義、クリストフ・エッシェンバッハ、小泉和裕、オッコ・カムが、それぞれ1曲ないし2曲、マーラーを指揮していたのである。そして91年9月にはエリアフ・インバルが都響へ初登場して《復活》を指揮、やがて新しいマーラー・シリーズを開始し、百花繚乱の趣を呈していくのであった。

若杉 弘
©堀田正實
なお彼はそのツィクルス以外でも、95年3月までの任期中に、86年7月の特別演奏会で《交響的前奏曲》(日本初演)と《子供の魔法の角笛》を、86年10月のサントリーホール・オープニングシリーズで《千人の交響曲》を指揮した他、87年にはクック版第10番の全曲と第4番を取り上げており、88年には第9番と《リュッケルトの詩による5つの歌》、92年には《嘆きの歌》を、94年にはベリオ編の《若き日の歌》(日本初演)を演奏している。そして任期最後の定期(95年3月)には、第9番を指揮したのだった。
これほどマーラーを数多く都響で指揮した彼だったが、その一方で、行きすぎた「マーラー・ブーム」という傾向には危惧を抱いていた。「あんまりイージーにマーラーをやり過ぎるのは危険だと思う。そうやってるといつかはお客様が、効用逓減の法則じゃないけど、もうマーラーは結構、という時期が来て、こんなに素晴らしい音楽なのに価値が下がってしまわないとも限らない」(同前)。
だがやはり、客演指揮者たちもマーラーの交響曲を指揮した。その80年代から90年にかけて、ベルティーニの他にも、アダム・フィッシャー、ヘルベルト・ケーゲル、山田一雄、井上道義、クリストフ・エッシェンバッハ、小泉和裕、オッコ・カムが、それぞれ1曲ないし2曲、マーラーを指揮していたのである。そして91年9月にはエリアフ・インバルが都響へ初登場して《復活》を指揮、やがて新しいマーラー・シリーズを開始し、百花繚乱の趣を呈していくのであった。
(東条碩夫)
記念コラム一覧
Anniversary Column Index