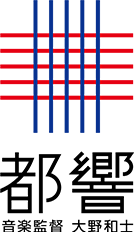アフタートーク|山田和樹指揮/三善晃「反戦三部作」
レポート2023年5月12日(金)東京都交響楽団第975回定期演奏会Aシリーズ
アフタートーク 東京文化会館大ホールホワイエ
山田和樹(指揮者)
国塩哲紀(都響 芸術主幹)
写真:堀田力丸

国塩「マエストロ、この演奏会は、コロナ禍による開催延期もあり、企画から足かけ7年でようやく実現しました。演奏を終えられてのお言葉をお願いします。」

山田「お言葉というか、都響がすごいなと思うのは、こんな演奏会の後に指揮者を引っ張り出して話をさせようというところですね。(会場爆笑、拍手)
とにかく、お話をいただいて、一も二もなくやりますと返事したのですけれど、本当はそんな簡単な話じゃないんですよ。それは、曲が大変だからというのもあるのですが、せっかくのアフタートークですから少し突っ込んだ話をすると、僕は日本フィルの指揮者であり、読響の指揮者であるわけですから(笑)、なかなかそちらを差し置いてというわけにはいかない。そうしますとここにいる国塩さんが、もちろんそんなことは百も承知で、ですから私(山田)が音楽監督兼理事長を務めている東京混声合唱団と一緒に、とおっしゃってくださって、これは山が動かないわけにはいかないと(笑)。」
国塩「日本フィルと読響にはちゃんとお断りを入れて、ご了承をいただいておりますので。日本フィルさん、読響さん、ありがとうございます。」
山田「本当そうですよね、仁義は切らないといけないですよね。そうやって最初の段階はクリアして、そして東混だけでは人数が足りないわけですから、さてどうしようと思って。今回、武蔵野音楽大学さんにお願いして本当によかった。それもあり、オーケストラの素晴らしさもあり。そして何より、曲の、美しさ…と言っていいのかな、難しさ、それは単純に譜面を音にすること、再現することの技術的な難しさもあるのですが、それ以上に精神的に求められるものがありますね。《レクイエム》はそのまま人の言葉―特攻隊員の遺書だったり―なんですけれど、《詩篇》は宗左近さんの世界ですから、単純に言葉だけでは、こちらもすぐにイメージがつかめなくて、その精神世界に入っていくということがとても難しいことですし、(《響紋》で)子供が出てくる意味だとか、最後の意味深な感じとか、いろいろなことがあり、あの三善晃という小柄な人のどこにこんなパワーがあるのだろうか、ということを感じながら演奏していました。今回幸いだったと思うのは、あまり演奏されない曲であるがゆえに、演奏機会が多い作品のようにきれいな印刷譜になっていなくて、三善先生の手書きのスコアで演奏することができたことで、それによって先生の声をほんの少しでも具現化できたのかな、と思っています。」

国塩「この3曲を続けて生で聴くという体験は、なかなかないことです。」
山田「史上2回目ですよね。前回は1985年、尾高忠明先生の指揮で、やはり東京文化会館でした。この中でその演奏会に来たという方はいらっしゃいますか?」(聴衆の何人かの手が挙がる)「ああ、いらっしゃいますね。素晴らしい。」
国塩「私ですら聴き終えて言葉もないという感じなので、マエストロはもっとお疲れかと思ったら、意外にお元気ですね(笑)。」
山田「そう、これが不思議なもので、…という話の前に、今回、三善晃先生のお墓参りに行こうと思ったのですが、お墓は軽井沢にあるということを知って、さすがにこの練習スケジュールの合間を縫っては難しく、まだ伺えてないので、いつか必ずと思っています。それで、不思議なものでという話ですが、先生のパワーに支えられたのもありますし、もちろんお客様にもなんですが、やっぱりね、人に助けられてということなんですよ。こんな重い音楽をやった後にこんなことを言ったら本当に申し訳ないのですが、ドラゴンボールってあるじゃないですか(笑)、あの孫悟空の必殺技に元気玉というのがあるんですよ。ご存じない方はごめんなさい(笑)。元気玉って、ものすごいパワーを集めて相手を攻撃するのですが、そのパワーというのは、生きとし生けるものすべての、例えば草や木からも少しずつエネルギーをもらって大きなエネルギーにして、という発想ですよね。まさしく今日がそんな感じです。僕一人ががんばる力というのは本当に限界があります。たった一人の人間ですから。けれど、求められていることは何千倍ものことだったりするわけで、そんなこととてもできないし。それでも、僕の役割としてああでもないこうでもないとうんうん唸りながらリハーサルをやっていく中で、合唱団の一人一人、オーケストラの一人一人、舞台上にいないスタッフの方々も含め、そして何より、今日、満席!完売!(会場拍手)のみなさまお一人お一人からパワーをいただかなかったらできなかった本番だったんですよ。そしてそのパワーは、今日会場にいらっしゃらない方からもいただいているんです。もっと言うと、亡くなっている方からも。僕をここまで育ててくれた方たちももうたくさん天国に行っています。だから僕は、本当の話、そういう方たちの写真をいつも燕尾服の内ポケットに入れて指揮しています。そういうパワーをいただかないと今日みたいな演奏はできないですよ。
我ながらひどい話で、僕のことだから当然本番は変わるんですけど、今日はその変わり幅がすごくて、場所によってはテンポが2倍ぐらい違ったりして、よくみなさんついて来られたなと(笑)。さすが都響、そして手前味噌ですがさすが東混、そして武蔵野音大のみなさん。そして何と言っても子供たちですね!(拍手) 今日はねー、やられたと思ったんですよー。子供たちが遅れて入ってくるのとか、小学生たちだけの声で始めてみようとかは僕のアイデアだったんですけど、本番になったらその子たち手をつないで、しかもその手を振りながら出てくるじゃないですかー。やられたなーと(笑)。それでカーテンコールの時にあれ誰のアイデアだったの?って長谷川久恵先生に聞いたら、『わ・た・し・よ!』って(爆笑、拍手)。そういったアイデアの総力戦ですよね。それは言葉にする方もいればしない方もいるんですが、それぞれが頭と心と体を最大限使って達成した演奏会だったなと思います。
そんなだから、僕は毎日くたくたになり果てて、初日の練習からダウンするんじゃないかと覚悟してたんですよ。本番の時にはもうどうなっちゃうかと…、まあ《レクイエム》が終わったらもう終わりなんですけどね(笑)。ましてこんな立ちっぱなしでアフタートークなんて絶対できないと思ってた(笑)。ところが、これがまた不思議だったんですが、やってる内容は、やれ死んだの、声がどうの、特攻隊がどうのとかそんなのばかりなのに、この練習期間中、本当に心穏やかに過ごせたんです。本番も、それこそパワーをいただいているから、《レクイエム》の後ですでに体は消耗しているんですが、着替えて、後半がスタートしたら、『あ、これはいけるな』と思えて、《響紋》が終わった時には元気になってるんですよね。まあ、今もう1回この演奏会をやれと言われてもできませんが(笑)、とにかく心穏やかにいられて、本番終わっても自分でも不思議なくらいこんなに元気でいられるのも、エネルギーをいただいているからだと思うし、それこそ三善晃先生の音楽がそうさせているんだと思います。
それで、三善晃先生の音楽というのは、とにかく矛盾なんですよ。《戦争を知らない子供たち》という歌があったように、もう少し経つと戦争の実体験がない人たちばかりになる。けれども、こういう音楽が遺っている限り我々は何か感じることができるし、何かイマジネーションを働かせることができる。だから、実体験を持つ人がいなくなっても、この作品が何かを伝えていくだろうという、三善晃先生のこのお考えが素晴らしい。ところが、じゃあ三善先生はなぜこの曲を書いたのか、書かねばならなかったのか、書きたかったのか、と考えると、本当にすごく酷な話で。簡単に言っちゃうと、戦争というものがなければこの3曲はないんですよ。もっと言えば、戦争がなければ三善先生はそもそも作曲家になっていなかったかもしれないじゃないですか。だけど、この作品があるから、今日我々が集って、一生懸命演奏して、心を一つにして、というところがあるじゃないですか。だから、先生の中にも壮大な矛盾があるんですよ、原点として。矛盾から始まるんです、すべて。だけど、三善先生は、とにかく生きること自体が矛盾でしょ、とおっしゃっています。生きることが矛盾だから、その矛盾を全部まとめて引き受けることが生きることかもしれないね、と。まさしくそう。人間は平和に暮らせばいいじゃないか。ではなぜ戦争をする? すべては矛盾から始まる。ひょっとしたら縄文時代そんな矛盾はなかったんじゃないか、いや縄文時代からその矛盾が始まっているんじゃないかとか、タイムスリップしてもわからない、解決しないような壮大な問題を堂々巡りするわけですよね。だけど、作品があることで今日集えたわけです。
今日思ったことがあって、指揮者の部屋にモニターがあって舞台が見えるのですが、演奏が始まる前に、まず合唱団員が出てくるでしょ? あれを見ただけで泣きそうになっちゃった。これはなんなのだろうと思った。一人一人がこれからやるぞって感じで出てきて、お客様が拍手してくださって、それでオーケストラが出てきて…。音楽って、この大きな人数が―舞台上だけではなくお客様も―心を一つにすることができるということなんです。

心を一つにすることはそんな簡単にできることではないのですが、音楽にはそれができる、もちろんそれも簡単じゃない、でもその可能性がある、ということを三善先生は一番お考えになっていたのではないか、と思いました。だから音楽を書き続けていたのではないでしょうか。」
国塩「あと一つ。最初にこの企画を持って行った時、会場は東京文化会館ですと申し上げたら、マエストロが、『文化会館!文化会館でなければいけない!文化会館でやることに意味がある!』とおっしゃったのをよくおぼえています。」

山田「そうだ!思い出した! 三善先生はここ東京文化会館の館長だったから。(会場から感嘆と納得のどよめき) ここでなきゃいけない。
これはどこまで言っていいのかわからないけど(笑)、三善先生は館長になってやりたいことがいっぱいあった。そろそろ日本から日本独自のものを発信していかなければならないという強い思いがあった。でも、いろいろなことがあって、横やりが入るわけです。具体的に何とは言いませんよ(笑)。三善先生は日本独自のものをとおっしゃっているんだけど、まわりからは依然として海外からのものをやりましょうという意見が強くて、それから先生は気持ちも体調もすぐれなくなってしまったと僕は思っていて、当時勝手に怒っていた。だから、今日、三善先生の作品だけを演奏して、満席になって、オーケストラも合唱団も渾身の演奏を繰り広げて、当時三善先生がここでやりたかったこと―もちろん実現なさったこともたくさんありますが―の一歩か半歩ぐらい先に進めたのではないかと思うとともに、こういうことをやり続けていかなければいけないなと思いました。(拍手)
今回僕は5月9日から19日まで10日間の日本滞在で、今日都響の演奏会、このあと「4コンダクターズ」という新作を発信する演奏会を東京オペラシティで、そして神戸文化ホール50周年記念コンサートで神戸室内管弦楽団を指揮するのですが、この3つの演奏会、全部日本人の作品なんです!(会場どよめき) 自分で隙間産業と言っています(爆笑)。券売などを考えると難しいのですが、それでも僕はやらなければならないと思って、細々でも続けて行こうと思っています。(拍手)
国塩「お疲れのところありがとうございました。山田和樹さんでした。」(拍手)
(おわり)